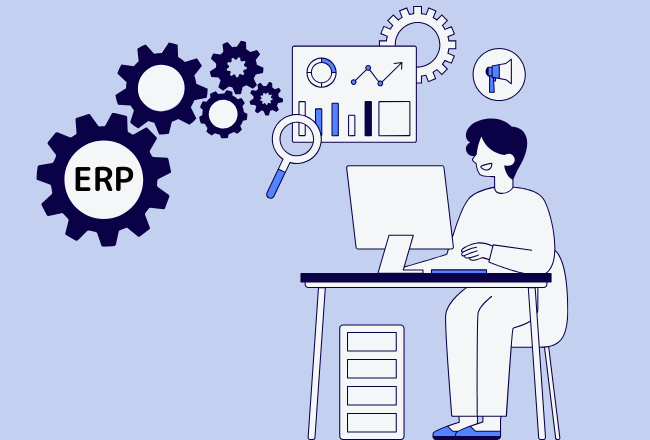経営管理DXの進め方(後編)経営管理DXの実効性を担保する4ステップ
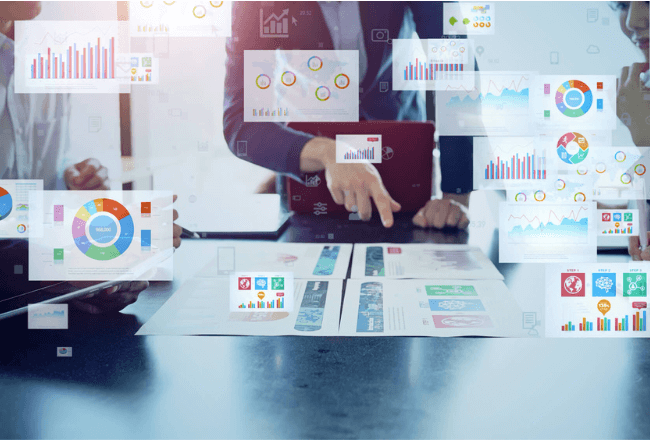
東京証券取引所が要請する「資本コストや株価を意識した経営」を実現するために、多くの企業が経営管理システムを導入し、経営管理DXを本格的に進めています。しかし経営管理DXを進める際には、さまざまな「壁」に直面することも事実です。
前編「経営管理システム導入時に直面する3つの壁とは」で解説したように、経営管理DXを進める際は3つの壁に直面します。こうした障壁を乗り越えるには、自社が抱える本質的な課題を踏まえて、システム実装の意義を明確化する必要があります。
後編では、自社の本質的な課題の解決につながる経営管理DXを通じて企業価値を向上させるためにとるべき4つのステップについて解説します。
経営管理DX推進に立ちはだかる3つの壁
前編でも解説した通り、経営管理DXの推進時には以下の3つの壁が立ちはだかる傾向にあります。
・データの壁:経営管理に必要なデータの有無や所在がわからない
・組織の壁:経営企画と事業部など、異なる組織間での動機付けが困難
・戦略の壁:システム導入の意義が曖昧になりやすい
経営管理DXを成功させ、高度な経理管理へ導くには、これらの壁に対して適切な対処が必要です。
壁を乗り越えて企業価値を向上させるための4つのステップ
データの壁・組織の壁・戦略の壁を乗り越えて経営管理DXを実現させるためには、大きく4つの工程を踏む必要があります。
ステップ1:実績データの可視化
まずは、自社が何を誰に販売し、どの程度の収益を出せているかを連結ベースで把握します。これによって、自社が持つ「稼ぐ力」の真の実力値を可視化できます。具体的には、以下の3点を明らかにします。
・原価(最小管理単位(品目/SKU単位)×原価の内訳(材料費や加工費など))
・物流費・販促費(商品軸・顧客軸の直課・配賦の整理とデータ集計)
・実績レポート(品目/SKU単位×顧客単位、売上/粗利/限界利益)
この際にデータの所在と信頼性を確認し、連結での事業および製品別の粗利を把握します。業務機能軸/サブシステムの単位で、実データの所在と活用可能性を調査する必要があります。
ステップ2:実績データの計画への活用
ステップ1で可視化した実績データを活用するための基盤を整備し、計画業務の質的向上を図ります。具体的には、以下のような対応が必要です。
・実績レポートを各部門がフィードバックして可用性を高める
・部門間の計画作成プロセスの前後関係を整理する
・PDCAサイクルを回すために追加で必要なデータや課題に対応する
各部門が計画作成に活用するための基盤を整備し、計画業務の質的向上を進めます。計画作成のために必要なデータである最小粒度の実績を各部門が計画作成に使い始めるのがこのステップです。
ステップ3:計画業務のシステム化
会社の計画作成プロセスを標準化します。これにより、販売計画と在庫計画、生産計画と調達計画といった各種計画間の整合性を取ります。
計画作成プロセスを標準化することで、本社が各種計画の適切性を確認したり、コントロールしたりできる状態になります。さらに、自社の何を分析する必要があるのかも見えてきます。
課題は、連結の予算の整合性が取れていないケースも多く見られます。地域統括CFOのトップダウン方針の醸成と、現場の移行課題を踏まえた落とし所の見定めが重要です。
ステップ4:将来シミュレーションの実現
ステップ1~3の内容を踏まえて、経営者の意思を反映した将来数値のシミュレーションができる仕組みを構築します。以下のようなことに取り組みます。
・システム化した計画業務の想定前提を柔軟に切り替えられる機能を実装する
・改善や強化をした実績・予算業務システムで差異要因分析を自動化・高度化する
自社の本質課題を探る際の注意点
前述の4ステップは、必ずしも順番に進める必要はありません。アプローチ方法は次の2パターンがあります。
アプローチ(1)「稼ぐ力の可視化」から「計画の高度化」へ:実績データの可視化からスタートし、段階的に計画業務の質を高めていくアプローチ
アプローチ(2)「計画の標準化」から「稼ぐ力の可視化」へ:まず計画業務を標準化し、その過程で見えてくる稼ぐ力の本質を明らかにしていくアプローチ
王道は、紹介したステップ1~4を順に進めるアプローチ(1)ですが、たとえば自社の状況に応じて例えばステップ3の計画業務のシステム化から取り組み、そのうえでステップ1の実績データの可視化に移るアプローチ(2)も一つの方法です。
どちらのアプローチを取るかは企業の現状や課題によって異なりますが、最終的にはすべてのステップの裏側にある本質的な課題に取り組むことが重要です。
本質課題の特定でシステム導入の目標設定が変わった事例
アバントがご支援した企業でも、プロジェクトの開始前に、本質的な課題を議論している中でどう課題を解決するのか、というアプローチ/システム実装の力点が変わった事例は多々存在します。
A社の場合:
当初、事業別ROICを導入することを目標としていました。しかし実際は連結での事業/製品別の粗利がわからないことが課題となっていることが判明したため、「稼ぐ力の可視化」を目標として、システム導入を決定しました。
B社の場合:
事業別ROIC×目標管理システムの実装を目指していましたが、本質の課題を探ったところ連結予算の整合性がとれていないことが判明しました。そこで、連結予算システムの実装に優先的に取り組む方向に切り替えました。
まとめ
経営管理DXは単にシステムを導入すれば済むものではなく、企業価値を向上させるための包括的な取り組みです。プロジェクトの開始から完了までにはいくつもの壁が立ちはだかりますが、今回紹介した4つのステップを踏んでいくことによって初めて目指すべき姿にたどり着くことができるでしょう。
ステップ1:実績データの可視化
ステップ2:実績データの計画への活用
ステップ3:計画業務のシステム化
ステップ4:将来シミュレーションの実現
4つのステップを通じて自社の本質的な課題を見極め、理想とする経営管理DXを実現させましょう。

経営管理において必要な財務・非財務情報を収集・統合し、多軸分析を行えるクラウドサービスです。1,200社超の支援実績から生み出された経営管理機能を持ち、データを収集する入力画面や、 90 種類の経営会議レポート・分析帳票などを標準搭載。設定のみで利用できます。